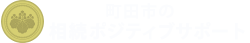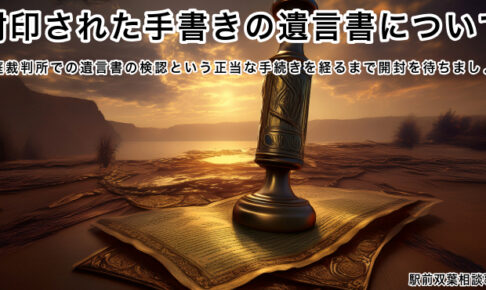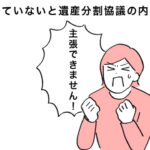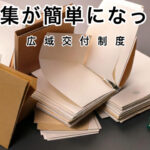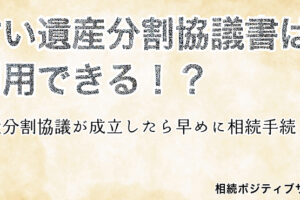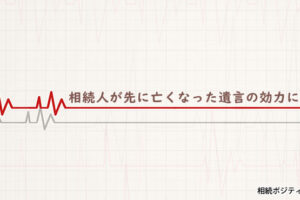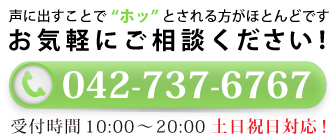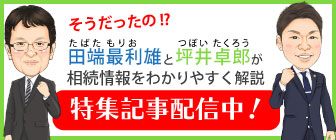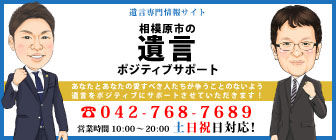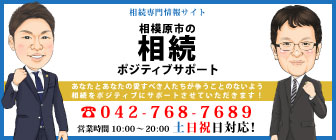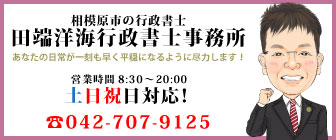自身が書いた遺言書を亡くなるまでに相続人に見られたくないという要望をもたれる方は一定数いらっしゃるようです。日本の民法ではそういったニーズに応えるための規定が存在するからです。
例えば公証役場で手続きを行う秘密証書遺言などの規定が存在します(民法970条)。秘密証書遺言は家庭裁判所の検認手続きの過程で開封をすることが定められています(民法1004条)。仮に家庭裁判所の関与なしに開封をしてしまった場合には5万円以下の過料に処されてしまいます(民法1005条)。
しかし秘密証書遺言は公証役場で公証人によって日付・遺言者の申述などが記載され、さらには遺言者と証人の署名がなされる厳格なものです。この秘密証書遺言を開封しようとする人は、よほどの悪意が無い限りはいないと思われます。
それでは公証役場の関与なく自宅にて作成した手書きの遺言を、手紙のような感覚で封筒の中に入れて糊などで閉じられた遺言書はどのように扱われるのでしょうか。実は秘密証書遺言と同じ扱いをされます。つまり家庭裁判所の関与なく勝手に開けてしまうと5万円以下の過料に処されてしまうのです。
一般の手紙のように単に糊で封されているため、何気なく開封してしまう相続人の方が見受けられます。亡くなった方の遺言の内容を早く確認したいのは当然の心理かもしれません。しかし封されていた遺言書を開けたことで他の相続人や家庭裁判所から遺言書について懐疑的な印象を持たれるのは損といえます。従って家庭裁判所での遺言書の検認という正当な手続きを経るまで開封を待ちましょう。
なお封が施された遺言を開封したからといって遺言書が無効になるわけではありません。開封後の遺言が自筆証書遺言の要件を満たしていれば遺言書としては有効です。