相続税がかかる人は一部だけ!?
相続が発生すると相続税がかかるものだとお考えの方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。実際、相続の相談の際に、相続税がどのくらいかかるのかと心配されている方は少なくありません。相続税には基礎控除があり、総資産がその範囲…
あなたの相続をポジティブにサポートします!
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
相続が発生すると相続税がかかるものだとお考えの方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。実際、相続の相談の際に、相続税がどのくらいかかるのかと心配されている方は少なくありません。相続税には基礎控除があり、総資産がその範囲…
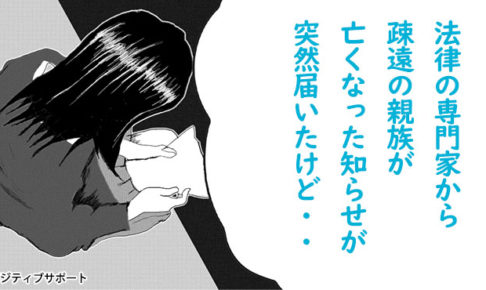 遺産整理
遺産整理
日本の相続に関する法律の規定は、相続が発生した場合に特定の相続人が他の相続人を出し抜いて単独で相続財産を独り占めする事が困難なようにできています(遺言がある場合を除く)。 仮に他の相続人に内緒で手続きをしようとしても、遺…
 遺産整理
遺産整理
相続が発生すると、配偶者と子が相続人になることは広く知られています。では、配偶者も死亡し子がいない場合は誰が相続人になるのでしょうか。相続分の割合も併せてみていきましょう。 下記の図の場合、被相続人(夫)「A」の相続人は…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
不動産の所有者が亡くなったときには、法務局で不動産の名義変更手続きを行う必要があります。この手続きは義務ではありませんが、名義変更手続きを行わないと不動産の売却や、不動産を貸していた場合には賃料の請求が困難となるため、我…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
ご家族が亡くなったときに行う相続手続き。何から始めれば良いのか、どこに相談すれば良いのかなど、初めての経験で分からないことだらけなのが相続です。ここでは、相続手続きの一般的な流れを説明します。 相続の発生(死亡)からの流…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
抵当権の債務者が亡くなり債務者が団体信用保険に入っていなかった場合、債権は消滅しないため抵当権者である債権者は、債務者の変更登記をすることを求めることがあります。法律上は、金銭債務は遺産分割の対象ではないため法定相続分の…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
子が未成年のうちに父が死亡した場合、相続手続きはどのような流れになるのでしょうか。 特別代理人を選任 未成年者は単独では有効な法律行為ができないため、相続手続きについても自己の意思によっては行えません。原則として、未成年…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
2019年8月9日、最高裁判所が初の判断を示しました。 「債務を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できる」 債務を残して死亡した伯父について、相続放棄をしないまま父親が死亡し、その債務を承継した子供は、いつまで相続放棄…
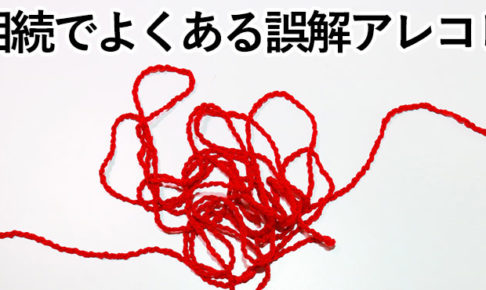 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
相続の内容は、お亡くなりになった人、順番、時期によって変わってきます。また、手続きに必要な書類や取得できる役所・機関も異なります。そのためか、相続手続きでは誤解が生じやすい傾向にあるようです。では、その中でも相談時に多い…
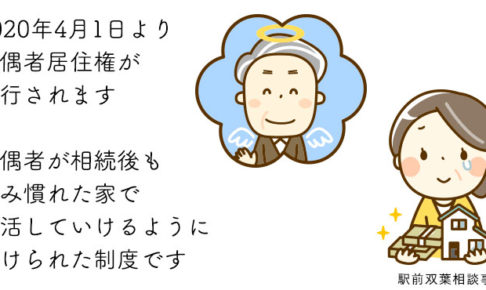 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
相続分は預貯金等の他、配偶者が居住する家も含めて他の相続人と遺産分割をするため、法定相続分とおりに分けようとすると家を売却せざるを得ないといった問題がありました。そこで2020年4月1日から施行されるのが「配偶者居住権」…
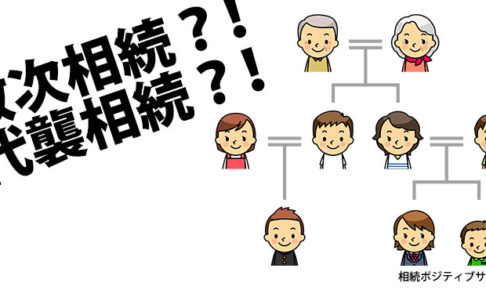 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
一般的に、相続では故人から配偶者または子供へ相続財産が継承されます。しかし、子供が親より先に亡くなってしまった場合は誰が親の財産を相続するのでしょうか。これを正確に判断するには、数次相続と代襲相続の2つのパターンの相続の…
 毎月更新の特集記事
毎月更新の特集記事
現行法では、夫の親や妻の親に相続が発生した際に、配偶者には相続権がありません。配偶者が、夫の親や妻の親(以下、「義親」といいます。)の療養介護をしていたとしても、遺産分割協議をするときには蚊帳の外になってしまうという、配…